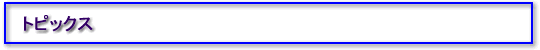青色発光ダイオードの200億円判決(東京地判H16.1.30)は、控訴審において8億円で和解したとは言え、それでも経済界に大きな衝撃を与えた。それは、金額もさることながら、特許法第35条第3項は、会社は職務発明について契約等の定めにより特許を受ける権利を承継したときには相当の対価を支払わなければならない旨を定めているが、その「相当の対価」の額は裁判所が判断するということであって、すなわち、会社は、訴訟が起こされて判決が出るまでは、得られた利益を再生産や新たな投資に注ぎ込むことができないということをも意味していたからだ。
しかし、この点に関しては平成16年の特許法改正により、「相当の対価」を労使の取り決めで定めることができるものとされた(同法同条第4項)。ただ、この第4項は、その定めが不合理でないかどうかを判断するのはやはり裁判所であり、その際には「労使間の協議の状況」、「策定された基準の開示の状況」、「従業者等からの意見の聴取の状況」等を考慮することとなっている点には、気を付けて読まなければならない。
とは言え、この法改正後に「対価の額」を争点とした訴訟事案は、少なくとも「判例」と呼べるものは出されていないので、一定の効果があったものと推測される。逆に言えば、相当の対価を労使の取り決めで定めていない場合は、冒頭の論に戻り、従業員(発明者)から訴訟を提起される危険に晒されているということでもある。特にベンチャー企業においてはアイデア一つで会社の存亡すら左右しかねないので、考えられる予防策は講じておくべきだろう。
現在、国の産業構造審議会が職務発明制度の見直しを始めている。「対価の額を会社(労使)が定めるのか、裁判所が判断するのか」についても論点に含まれているので、そういった観点からも、今後の議論の行方を見守っていきたい。
(情報提供:社会保険労務士 神田 一樹)
情報提供:上場.com
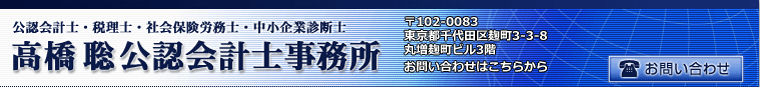


 当事務所は上場ドットコム
当事務所は上場ドットコム