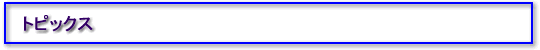株式会社に現金ではなく土地などの不動産を提供して、その代わりにその会社の株式をもらい受ける、いわゆる現物出資をしたときの経費について新たな取扱いを関東信越国税局が示しました。
株式会社が個人から土地の現物出資を受ける場合、その土地の所有権移転登記や裁判所に対して検査役の選任の申立てをして、現物出資財産の価額を調査してもらわなければなりません。所有権移転登記は問題ないのですが、裁判所に検査役の選任の申立てをするとなると少々面倒な手続きが必要となります。そこで、会社法では、現物出資した土地の価額について不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、その価額が相当であることについて税理士に証明してもらえば、現物出資で得た財産の価額について検査役の調査は不要とされています。
税務上、注意しなければならないのは、現物出資をした個人が土地と引換えに株式を受け取ることから、もらい受けた株式の総額が提供した土地の売却代金とみなされ、その分を譲渡所得として申告しなければならないということです。譲渡所得の計算上、費用をなるべく多く積み込むことができれば納める税金も少なくて済みます。そこで、関東信越国税局に寄せられた納税者からの質問は「現物出資をした個人が、所有権の移転登記に関する登録免許税や不動産鑑定料および税理士報酬を支払った場合、譲渡所得の計算上、それらを費用として取扱っても良いか」という内容でした。
それに対して同国税局は「登録免許税については費用と認めるが、税理士報酬及び不動産鑑定料は、現物出資を受けた株式会社がその税理士と不動産鑑定士に支払うべきものである。したがって、たとえ契約に基づいて出資者が負担したとしても、現物出資を実現するために必要であった費用に該当するとは認められない」という見解を示しています。
三井住友フィナンシャルグループのシンクタンク(株)日本総合研究所(日本総研)が、企業への補助金依存の温暖化対策では目標達成は難しいことを結論づけた「京都議定書削減目標の達成可能性と中期目標の方向性」と題するレポートを公表しました。
日本総研の調べでは、2004年以降、燃焼起源の二酸化炭素の排出原単位は、年間でマイナス2.3%も改善していて、それはオイルショック期の年間マイナス3.5%に次ぐものだとしています。
しかし、2020年の中期目標として民主党が掲げている「1990年比25%削減(真水は15%)」を達成するためには、実質経済成長率を+1.3%としても、原単位を年間マイナス2.7%で改善し続けることが必要で、これまで以上の取り組み方が不可欠であるとしました。
そこで、2020年に1990年比マイナス25%と年率2%の経済成長を両立させるための政策として日本総研が同レポートのなかで要求したのは、自然エネルギーの導入促進などに加えて「二酸化炭素排出原単位が低く、付加価値額の高い産業を機軸とした炭素制約下の成長戦略」、「中長期的に調達コストの上昇が予想されるCDM(クリーン開発メカニズム)の活用は、あくまで『補足的』とすること」、「物流部門のモーダルシフトについては、規制緩和などによりトラック輸送からのシフトを促すこと」、「電力を中心としつつも、都市ガス、LPGのバランスに配慮した需給構造とすべき」などです。
さらに、日本総研は同レポートで「わが国が、世界最高水準の削減目標を達成するためには、あらゆる経済・財政政策を、二酸化炭素排出量への影響と関連付けて立案する必要がある。補助金依存の温暖化対策は、財政への負担が大きく持続性に乏しい。『気候変動交渉に関する日米共同メッセージ』に基づく2050年8割削減という長期目標を踏まえれば、炭素税や規制緩和などによる持続性の高い政策が必要」と強調しています。
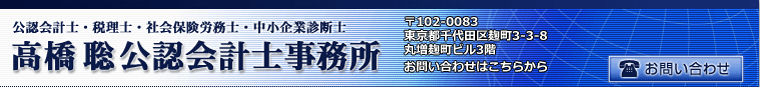


 当事務所は上場ドットコム
当事務所は上場ドットコム