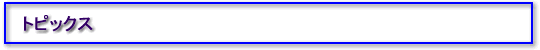平成19年度税制改正で減価償却資産の償却方法が大幅に改正され、100%償却が可能となりましたが、償却限度額95%を超えて償却し始めるときのタイミングで戸惑う納税者がクローズアップされています。
減価償却とは、業務に使うことによって価値が減少する資産、いわゆる減価償却資産について、その取得価額を使用可能期間に費用として配分する計算手続きのことです。そして、実際に償却するときには償却限度額というものが規定されていました。その償却限度額については、資産を除却しない限り、減価償却資産の取得価額の95%までとされていました。
それが平成19年度税制改正で100%償却できることになったのです。具体的には、95%まで償却が進んだ資産は、それ以後5年間で全額均等償却可能とされ、1円(備忘価額)まで償却できることになりました。
そこで、個人事業者の間では、95%まで償却したらその年から5年間の均等償却が適用できると思い込んでいる人が意外と多くいます。これについて国税庁では「5年均等償却は、減価償却費の累計額が取得価額の95%相当額に達した年分の翌年分から適用されます」と説明しています。これは、「平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が取得価額の95%相当額に達している場合には、その達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却する」とされている所得税法施行令第134条第2項に基づいています。
(社)日本経済団体連合会(日本経団連、御手洗 冨士夫会長)が「税・財政・社会保障制度の一体改革に関する提言」を発表しました。
日本経団連の今回の「税・財政・社会保障制度の一体改革に関する提言」で注目されているのは、「当面の一体改革の具体策」です。そこでは、「社会保障制度の綻び解消や基礎年金の安定的財源確保、基礎的財政収支の黒字化などに向け、2009年度から2011年度の3年間を第一フェーズと位置づけて、税・財政・社会保障の改革を一体的かつ連続的に措置すべき」としています。ただし実施に当たって「経済情勢や歳出入への影響に注意し、柔軟かつ機動的な判断が必要になる」ことも付け加えています。
そして、2010年度、または遅くとも2011年度を目途に「中低所得者層を対象とした、5年程度の時限措置として消費税率1%相当規模の大胆な所得税の定額減税の実施(例えば、世帯当たり10万円程度)」や「社会保障制度や少子化対策、基礎的財政収支の黒字化に向け、消費税率を5%引き上げ10%にし、地方の財源確保と活性化に資するよう、国7%、地方3%の配分を行う。同時に基礎的な食料品等に関しては軽減税率(現行の5%を維持)を検討する」、「社会保障番号を活用した納税者番号制度の導入する」ことを要求しています。
一方、法人企業については、「諸外国で進む法人実効税率引き下げ競争への対応はわが国経済成長のための主要課題である」とした上で、「地方法人特別税の廃止や地方法人二税の見直し」、「欠損法人による適切な応益負担」などを求めました。
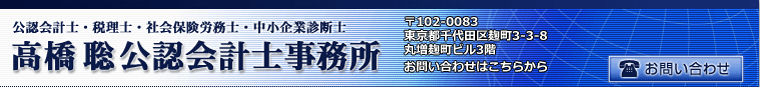
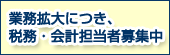

 当事務所は上場ドットコム
当事務所は上場ドットコム