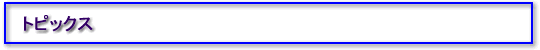民間調査機関の帝国データバンクが、このほど、全国2万1,040社を対象に消費税や税制に対する意識調査を実施した結果を公表しました。それによると、5社に1社が消費税率10%を念頭においていることが分かります。
帝国データバンクが、今年7月18日から同月31日にわたって「消費税や税制に対する企業の意識調査」を実施しました。有効回答数は1万651社でした。
同意識調査の結果を見てみると、「消費税率が引き上げられることについて」の質問で、「賛成」と回答した企業は3,145社(29.5%)でした。逆に、「反対」とした企業は5,336社(50.1%)で、半数の企業が消費税率の引き上げに対して反対の意思表示をする一方で、3割程度の企業が賛意を示しています。
消費税率の引き上げに「反対」した理由としては「歳出削減が進んでいない」が5,336社中4,277社(80.2%)で最も多く、次いで「さらに景気が悪くなる」3,563社(66.8%)、「政治不信」2,683社(50.3%)といった順番でした。帝国データバンクでは「景気が一層後退することに懸念を感じているほかに、歳出削減が進んでいないなかで政治や行政に対する不信感が反対理由の上位に挙がった」と分析しています。また、「消費税率が将来引き上げられるとき」の質問では、「税率10%にすべき」と2,266社(21.3%)が回答、5社に1社が次の税率改定では「10%」を念頭においていました。
なお、税制改正への期待では、「道路特定財源の一般財源化への具体案」3,918社(36.8%)、「子育て世代への優遇策」3,833社(36.0%)、「たばこ税増税」3,599社(33.8%)、「消費税の見直し(食料など生活必需品への軽減税率の導入)」3,409社(32.0%)で3割を超えています。
個人事業者が従業員に支払う退職金は経費として計上できます。しかしそれは、事業がうまくいっているときであって、事業主の不慮の事故で廃業に追い込まれた場合は、事業主の遺産から解雇した従業員に退職金を支払うことになります。問題は、その従業員に支払った退職金が相続税の計算上、債務控除できるかどうかです。
このところ、地震や豪雨などの災害で命を落とす事業主が多くいることから、自分にもしもの場合があったときのことを考える事業主たちから、そういった声が聞かれるわけです。
その疑問について国税庁では「被相続人の死亡によって事業を廃止して、被相続人が雇用していた従業員を解雇するときに、その従業員に支給した退職金は、被相続人の生前事業を営む期間中の労務の対価であり、被相続人の債務として確実なものであると認められるので、相続税の課税価格の計算においては、その金額を控除しても差し支えない」と回答しています。
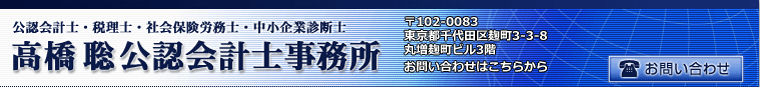
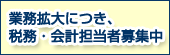

 当事務所は上場ドットコム
当事務所は上場ドットコム