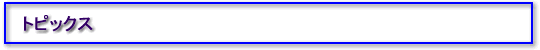5,000円以下の飲食費の経費算入制度で交際費減少―中小企業実態調査
08月04日
中小企業庁が「平成19年度の中小企業実態基本調査」の結果を公表しました。そこには、平成18年度税制改正で導入された交際費課税の軽減措置の効果が現れています。
中小企業実態基本調査は、中小企業庁が平成16年度から毎年実施しているものですが、今回の調査報告書は、平成18年度の中小企業の決算データを基に提出された回答を集計し、取りまとめたものです。調査のベースは、売上高を基に、目標精度(標準誤差率)を業種分類(産業大分類)ごとに概ね5%、業種分類・従業者規模区分ごとに概ね8%として標本数を算出し、55,896件から回答を得ています。
今回の調査で注目されるのは、平成18年度税制改正で導入された「5,000円以下の飲食費の経費化」です。この制度の効果がどの程度あったかが問われました。
今回の調査における中小企業の営業費用の構成は、売上原価が78.4%で、販売費及び一般管理費は21.6%を占めました。売上原価の内訳では、商品仕入原価が42.2%と最も高く、次いで材料費11.8%、外注費10.9%の順となっています。販管費の内訳は、人件費が10.5%と約5割を占め、次いで地代家賃が1.3%、減価償却費が0.9%、運賃荷造費が0.9%となっています。そして、その販管費のなかに交際費が含まれているわけですが、今回の調査結果では、経費全体に占める交際費は0.3%でした。平成18年度の調査では、経費全体の中で交際費は0.4%だったことから、0.1%減ったことになります。不安定な景気から交際費を抑えた企業が増えた感もありますが、金額にすると0.1%は約300億円で、1社あたり年間で約53万円減ったことになることから、5,000円以下の飲食費の経費化はある程度効果があったと見られています。
相続税の課税方式変更で日税連が財務省と意見交換
08月04日
日本税理士会連合会(池田隼啓会長、日税連)の調査研究部(杉田宗久部長)が、7月31日に平成21年度税制改正に向けて検討されている相続税の課税方式の変更について、財務省主税局と2回目の意見交換を行いました。
今回の意見交換の内容については、公開されておらず、日税連の調査研究部が作成した資料が現時点で公開されているだけです。その資料は、相続税の課税方式を本来の遺産取得課税方式に改めることにした場合の現時点における主な法制的・実務的論点について、有識者からのヒアリング結果などを踏まえて整理されたものです。
同資料では、例えば「仮装分割・仮装未分割等への対応」と題して検証。現行制度では、相続税の総額について、合計課税価格に相当する金額を相続人が法定相続分に応じて取得したものとして算出し、各取得者の相続税額は、相続税の総額に各取得者の取得財産の課税価格が合計課税価格に占める割合を乗じて算出します。これについて、遺産取得者課税に変わると「現行課税方式の下では、相続税の総額は遺産がどのように分割されたかのかに関わらず一定であるが、課税方式を見直した場合には、相続税の総額は遺産分割のされ方に影響を受けることになることを踏まえ、仮装分割や仮装未分割等による租税回避行為が発生する」という問題が生じる可能性があることを指摘。
これについて、有識者の考え方は、「仮装分割等の租税回避行為に対しては、適切な調査により対応する必要があると考えられる。他方、納税者に過度の負担をかけることを避けるため、現行以上に効率的・効果的な調査を行う必要があることから、例えば、資料情報の一層の充実を図ることとしてはどうか」としています。
今回の意見交換の内容については、公開されておらず、日税連の調査研究部が作成した資料が現時点で公開されているだけです。その資料は、相続税の課税方式を本来の遺産取得課税方式に改めることにした場合の現時点における主な法制的・実務的論点について、有識者からのヒアリング結果などを踏まえて整理されたものです。
同資料では、例えば「仮装分割・仮装未分割等への対応」と題して検証。現行制度では、相続税の総額について、合計課税価格に相当する金額を相続人が法定相続分に応じて取得したものとして算出し、各取得者の相続税額は、相続税の総額に各取得者の取得財産の課税価格が合計課税価格に占める割合を乗じて算出します。これについて、遺産取得者課税に変わると「現行課税方式の下では、相続税の総額は遺産がどのように分割されたかのかに関わらず一定であるが、課税方式を見直した場合には、相続税の総額は遺産分割のされ方に影響を受けることになることを踏まえ、仮装分割や仮装未分割等による租税回避行為が発生する」という問題が生じる可能性があることを指摘。
これについて、有識者の考え方は、「仮装分割等の租税回避行為に対しては、適切な調査により対応する必要があると考えられる。他方、納税者に過度の負担をかけることを避けるため、現行以上に効率的・効果的な調査を行う必要があることから、例えば、資料情報の一層の充実を図ることとしてはどうか」としています。
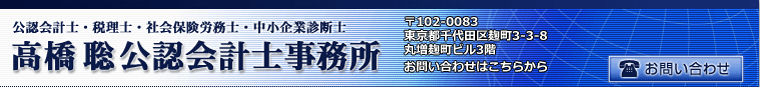
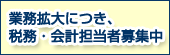

 当事務所は上場ドットコム
当事務所は上場ドットコム